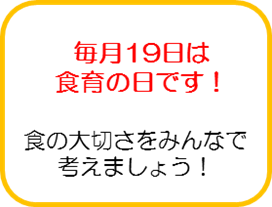本文
つないで備える 日々の食・非常時の食(令和7年度11月号)
乳幼児のための非常食とは?何をどのくらい備蓄しておけばいい?
いざというときのため、赤ちゃんやお子さんのための非常食は、どんなものをどのくらい備蓄していますか?
非常時には、お子さんはおとなのようにがまんができなかったり、体調を崩しやすかったりすることなども想定して、あらかじめ準備をしておくことがポイントです。
いつ起こるかわからない災害時に赤ちゃんを守るためには、普段から食べ慣れている食べ物を備蓄しておくことや、月齢に応じた離乳食・幼児食を成長に合わせて準備しておくことが必要不可欠です。アレルギーのあるお子さんには備えがより大切なものになります。
非常食は最低3日分の備蓄が推奨されていますが、災害の規模などにもよって異なり、2週間ほどの備えがあればなおよいともいわれます。特に赤ちゃんやお子さんがいるご家庭では、規模などにかかわらず少なくとも2週間程度の備蓄が必要とされています。
ベビーフードには、野菜などが裏ごしされてフリーズドライにされたものや、お湯で溶くだけのフレーク状のおかゆや野菜、粉末の野菜スープといった軽くて持ち運べるもの、レトルトパウチのものなど、様々な形状・形態のものがあります。食べる量や種類も個人によって異なるため、我が子に合わせての準備が大切です。
また、乳児用ミルクは、粉ミルクだけではなく、お湯が使えない環境でも授乳ができる液体ミルクも便利です。重さがあるため持ち運べる量を吟味してバッグに入れておき、残りは家庭内の置き場所に備蓄しておきましょう。
日々の食と非常時の食をつないでおくと安心!「備える食育」
非常用の食品を備蓄しておくだけでは、実は十分とはいえません。いざというときに、備蓄しておいた食品をお子さんが食べられるようにしておくこと、実際に食べられるものを備えておくことがとても重要です。非常食を特別に備蓄しておくのではなく、いろいろな種類を多めに買い置きしておき、普段から賞味期限が来る前に使っては補充する方法(ローリングストック)を活用しながら、食べられるものを増やしておきましょう。
お子さんの成長に伴って、好みの形状や食品も変わっていくもの。現状に合わせて定期的に入れ替えるようにしておくと安心です。
授乳に関しては、小さな赤ちゃんでもコップやスプーンを使って行うカップフィーディングという方法があります。哺乳瓶がなくても清潔な紙コップがあれば授乳できるため、いざというときのために練習しておくとよいでしょう。
カセットコンロでいろいろな料理を同時調理ができる「パッククッキング」もおすすめです。耐熱性の高密度ポリエチレン製の袋に食材を入れて湯煎調理するため、時短・節約などの面でも効果が見込まれ、普段から取り組まれている方も増えています。簡単調理なので、お子さんとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
パッククッキング おかゆ


「モノ」だけでなく、食育の面からも、日々の食と非常時の食をつなぐ「備える食育」を意識しておきたいですね。
毎月開催!「カンガルーぱくぱく教室 調理編」
高槻市立子育て総合支援センター「カンガルーの森」では、毎月離乳食や幼児食のクッキング講座「カンガルーぱくぱく教室 調理編」を開催しています。離乳食中期(7・8か月)、後期(9から11か月)、完了期(1歳)、幼児期(2歳から就学前)の各クラスがあり、親の料理を作りながら、食材を取り分けて子どもの料理も作ります。親の料理は1歳児が食べられる味付けを基本にし、離乳食期のお子さんを持つ方にも完了期からの味加減を体験していただいています。
試食では、お子さんが食べている様子を見ながら栄養士の個別相談などもでき、実際に嚙めているのか、食べる量はこのくらいでもよいのか、なども確認していただけます。だし取りなどの調理の基礎の確認、取り分けのタイミング、とろみ付けなど食べやすくするコツなどを実際に体験できてよかった、だしが効いているので子どもがよく食べた、このくらいの形状でも食べられるのがわかったなど、好評をいただいています。
令和7年10月、11月実施メニュー
【1歳から大人】
・炊き込みちらし寿司 ・ブロッコリーの和風ツナチーズ和え
・あんかけ小田巻蒸し ・かぼちゃようかん
【1歳からおとな】

【9から11か月】
・小田巻蒸し ・かぼちゃとツナのお焼き
・スティック野菜 ・軟飯からおかゆ
【9から11か月】

【7,8か月】
・ブロッコリーとツナのうま煮 ・かぼちゃの白和え
・5倍かゆ
【7,8か月】

詳細はたかつきDAYS12月号、高槻市ホームページ等をご覧ください。ご参加をお待ちしています。
記事作成:子育て支援課(Tel:072-686-3030)