本文
特殊車両通行許可制度
重量、幅、高さ等が車両制限令に定められた一般的制限値を超えるクレーン車、セミトレーラー等は「特殊な車両」として扱われます。
「特殊な車両」が通行すると、道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、道路を通行する際に道路管理者の許可を得なければなりません(道路法第47条)。
車両の一般的制限値とは
| 幅 | 2.5メートル |
|---|---|
| 総重量 | 20トン |
| 軸重 | 10トン |
| 輪荷重 | 5トン |
| 隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン |
| 高さ | 3.8メートル |
| 長さ | 12メートル |
| 最小回転半径 | 12メートル |
この表の中の値がひとつでも一般的制限値を超えると、道路管理者の許可を受けなければなりません。
特殊車両の申請をするには
(1)一つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は、その道路管理者に申請します。
例)
- 国道のみを通行する場合・・・大阪国道事務所へ
- 大阪府道のみを通行する場合・・・大阪府下の土木事務所へ
- 高槻市道のみを通行する場合・・・高槻市役所へ
(2)二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合は、どちらの道路管理者にも申請することができます(一括申請)。
例)
- 国道と都道府県道の二つを通行する場合・・・国土交通省か都道府県下の土木事務所のどちらかへ
- 指定市(政令指定都市)が管理する道路と都道府県道の二つを通行する場合・・・指定市か都道府県下の土木事務所のどちらかへ
ただし、高槻市を含む指定市以外の市町村はその市が管理する道路にしか許可が出せません。
例:高槻市が管理する道路と都道府県道の二つを通行する場合・・・都道府県下の土木事務所へ
では、この場合の申請は?
ケース1
出発地から目的地までA道路(高槻市道)、B道(大阪府道)、C(国道)、D(大阪市道)を通る。
注釈
- A道路(高槻市道):指定市以外の市町村が管理する道路
- B道(大阪府道):都道府県が管理する道路
- C(国道):国土交通省が管理する道路
- D(大阪市道):指定市が管理する道路
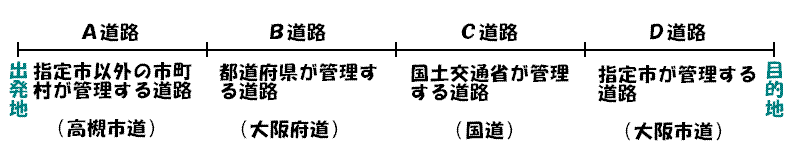
- 国土交通省、大阪府、大阪市は、A道路からD道路の全道路について申請の受付をすることができます。
A道路からD道路の全線について申請をする場合は、大阪国道事務所、大阪府下の土木事務所、大阪市役所のいずれかへ - 高槻市はA道路についてのみ申請の受付をすることができます。
A道路のみの申請をする場合は、高槻市役所へ
ケース2
出発地から目的地までE道路(大阪府道)、F道路(国道)を通る。
注釈
- E道路(大阪府道):都道府県が管理する道路
- F道路(国道):国土交通省が管理する道路
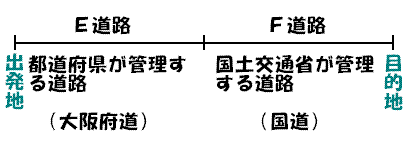
国土交通省と大阪府は、E道路、F道路の両方について申請の受付をすることができます。
E道路からF道路の全線について申請する場合は、大阪国道事務所または大阪府下の土木事務所へ
ケース3
出発地から目的地までG道路(島本町道)、H道路(高槻市道)を通る。
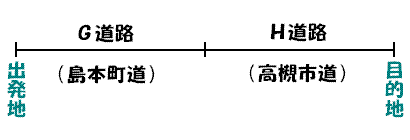
島本町はG道路についてのみ、高槻市はH道路についてのみ、申請の受付をすることができます。
G道路の申請は島本町役場、H道路の申請は高槻市役所へ
申請の種類
- 普通申請・・・申請する車両の台数が1台の場合
- 包括申請・・・申請する車両の台数が2台以上の場合
(ただし、車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同一のものに限ります)
注意:申請する車両が複数の場合は、申請する車両の車両諸元の中で車両の幅、総重量、高さ、長さ、最大軸重は最大の値を、最遠軸距、最小隣接軸重等は最小の値を記入して下さい。その上で、「車両の諸元に関する説明書(包括用)」と「車両内訳書」に各車両の諸元を記入して下さい。
申請に必要な書類
下記の書類を、正副の2部用意してください。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書(包括申請の場合のみ)
- 軌跡図(超寸法車両のみ)
特殊車両通行許可申請書・車両の諸元に関する説明書・車両内訳書・通行経路表記入様式については、以下からダウンロードできます。

