本文
高槻市市民公益活動推進方針 市民公益活動の推進
目次
第1 方針策定の趣旨
第2 市民公益活動推進の基本的考え方
- 市民公益活動の位置付け
- 市民公益活動推進の意義
- 市民公益活動団体との協働
第3 市民公益活動の基本的促進策
- 活動拠点としての市民公益活動サポートセンターの充実
- 情報の収集・提供
- 相談体制の充実
- 広報・啓発の充実
- 人材の育成
- 公共施設活用のためのサポート
- 資金面での情報提供
第4 市民公益活動サポートセンターの役割と充実の方向性
- サポートセンターの役割
- サポートセンターの運営
- 既存の関係機関等との関係
資料
- ボランティアについて
- NPOについて
- 特定非営利活動促進法(NPO法)について
第1 方針策定の趣旨
近年、市民自身の自発的な社会参加の機運の高まりとともにボランティア振興方策の推進や、企業の社会貢献活動の定着が進みました。平成7年(1995年)に起った阪神・淡路大震災では、多くのボランティアやNPOなどが多様な活動を展開し、注目を集めることになりました。
こうしたことを背景に、平成10年(1998年)12月、「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号、通称NPO法)が施行され、これを契機に福祉、環境、まちづくりなどのさまざまな分野で特定非営利活動法人(通称NPO法人)を始め、ボランティアやNPOの活動が広がりを見せています。
社会的に必要とされるサービスの提供や社会の諸課題解決などを自ら担おうとするこれらの活動の推進が、今後のまちづくりにとって必要となっています。
高槻市は、平成13年(2001年)1月に第4次総合計画(以下「総合計画」という。)を決定しました。この計画に、「たかつきリーディングプラン」の一つとして「ボランティア・NPO活動支援プラン」を位置付け、ボランティアやNPOの活動に参加しやすい環境づくりを進めることなどを盛り込んでいます。
同年5月には、様々な分野の市民で構成される高槻市市民活動促進懇話会を設置しました。この懇話会では、約11か月にわたり活動の活性化策などについて検討がなされ、平成14年3月に「市民活動促進懇話会報告書―新しい風をこのまちに」がまとめられました。
この報告書に示された考え方を踏まえ、ボランティアやNPOなどの市民公益活動との連携を通して、市民と行政との協働の推進を図るとともに、こうした活動を推進する環境の整備のため、市民公益活動推進方針を策定するものです。
なお、本方針については、今後の本市における市民公益活動の進展や協働の広がり、関連法令の動きなどによる状況の変化を踏まえ、必要に応じて内容を見直すこととします。
第2 市民公益活動推進の基本的考え方
1 市民公益活動の位置付け
市民の自主的活動は、ボランティア(資料1参照)やNPO(資料2、資料3参照)の活動の他、地縁を基にして交流や地域防災、環境問題など地域の課題全般に関わるコミュニティ組織の活動、更には、生活の豊かさや自己実現を目指す文化・スポーツなどの社会教育・生涯学習活動など、様々な形態で展開されています。
本推進方針では、市民活動のなかでも、「様々な社会経済的な課題の解決に向けて、市民が自主的・主体的に、営利を目的とせず、公益(不特定多数の人の利益)の増進に寄与することを目的として取組むボランティアやNPOの社会貢献活動」を「市民公益活動」と位置付け、その対象領域とします。そして、市民公益活動を継続的に行う民間団体を市民公益活動団体とします。いわゆる協働のパートナーとなる団体ですが、この場合、宗教活動や政治活動を主な目的とする団体、特定の個人や団体の利益を目的とする団体は含まないものとします。
なお、市民公益活動は、市民活動促進懇話会報告書が定義した「市民活動」と同様の活動を指しています。
個別の社会的目的をもって活動する市民公益活動と、地域課題包括対応型の活動を行うコミュニティ活動とでは、行動原理や組織的性格などを異にするものですが、地域のボランティア精神に支えられた社会貢献活動という点では同一の取組みでもあります。さらに、社会教育・生涯学習活動についても、活動の発展のなかから学習グループや団体を通して社会貢献活動に取組むなど社会的役割を果たす側面もあります。
こうしたことから、市民公益活動の推進については、単に団体の性格から判断するのではなく、行われる活動の内容に着目し、主として市民公益活動を目的としない団体・組織とも、連携やネットワーク化が図られるような視点が重要です。
2 市民公益活動推進の意義
(1)多様な市民サービスを創出
市民公益活動団体は、「自発性」や「機動性」、「効率性」、「先駆性」、「専門性」などの特性をもち、「個別対応の容易さ」や活動の「多彩さ」などを活かして、多様な市民サービスを創出する可能性を持っています。こうした特性は、環境にやさしいまちづくりや子育て支援、高齢者介護関連など市民自らの手でサービスを提供する領域において力を発揮することになります。
(2)市民の社会参加の機会を拡げる
市民公益活動は、生きがいや人と人とのつながりを求めて社会貢献活動に参加したいという参加欲求に応え、市民の主体的参加領域を拡大して活動の場を提供するという意味で重要な役割を担っています。
(3)市民の自治意識の向上
市民は、これまで公共サービスの受け手としての立場が強調され、公共サービスの担い手でもあるという面が看過されがちでした。市民公益活動は、社会的に必要とされるサービスの提供を担うことを通じて、市民のまちづくりへの参加意識、自治意識を高める糸口となります。
(4)地域社会における新たな経済活動の担い手
近畿経済産業局が新たな地域経済社会構築の方向性についてまとめた、「近畿地域における『自律循環型地域経済システム』の構築に向けた調査研究報告書」(平成13年3月)が示しているように、近年、新たな産業・雇用の創出、財政の健全化や地元主体の地域づくり、環境にやさしい社会経済活動、生活者・個人を重視した社会経済構造への変化などの課題を克服するために、地域経済の自律力・内発力を高めるような新たな地域経済システムの構築が求められています。こうしたなかで、地域の様々な問題解決をめざしたボランティア活動が、ビジネスにつながり、新たなコミュニティビジネスも生まれてきています。このような地域社会における新たな経済活動の担い手として、市民公益活動団体が、重要な役割を果たすようになってきています。
3 市民公益活動団体との協働
(1)協働の意義
市民公益活動団体と行政との協働は、「相互に特性を認め合い、それぞれの役割と責任を果たしながら、共通する社会的課題の解決や目的の実現に向けて、各種事業の実施、サービスの提供を行うなどの関係」を指します。
総合計画では、市民と行政がそれぞれの役割と責任を果たしながら、協働してまちづくりを進める考え方を示しています。こうしたまちづくりには、市民一人ひとりの参画はもちろんのことですが、様々な社会的目的の実現を目指して活動を行う市民公益活動団体との協働の推進が重要になります。
協働事業には、市民のボランティア参加や事業協力から、市民公益活動団体との事業の共催や事業委託まで多様な形態があります。本市の各部局が行っている市民公益活動団体等との協力関係による各種サービス提供や市民参加型の事業については、平成14年度に調査を実施したところ、全体で79の事業例が報告されています(末尾参照)。
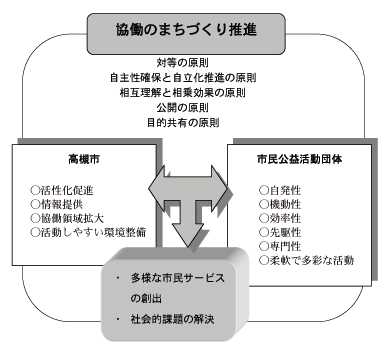
(2)協働の推進
市民公益活動団体と行政との協働関係の構築は、市民参加のまちづくりや地域ニーズ対応領域を中心に、機動性、効率性といった市民公益活動の特性を活かし、柔軟で安定した市民サービスを実現するという意味から、施策実施についての積極的な情報提供、協働する領域の拡大と活動しやすい環境の整備などにより、一層の推進を図る必要があります。
従来行政が行ってきた分野にあっても、市民公益活動団体が担うことができるサービス等については、積極的に団体に委ねていく視点が必要です。
(3)協働の原則
市民公益活動団体と行政との協働の実現に当たっては次のような原則に基づき進める必要があります。
- 対等の原則
- 市民公益活動団体と行政が協働して課題解決等に向けた取組みをする際には、協働の相手方を自立した存在と認識し、相互が上下関係ではなく横の関係にあることを前提として、対等に連携することが必要です。
- 自主性確保と自立化推進の原則
- 協働にあたって、市民公益活動団体が、自主的な立場で自立して事業を展開できることが必要であり、事業の委託などにあたっても相互に依存や癒着関係に陥らないような視点が必要です。
- 相互理解と相乗効果の原則
- 市民公益活動団体と行政とは意思決定の仕組みや行動原理が異なるため、相互の特性を理解し合い、社会的課題等の解決目標を共有して、両者が単独・独自に事業を進める以上の効果を生み出すよう努めることが必要です。
- 公開の原則
- 特定の市民公益活動団体と行政が協働を行う時は、両者の関係は、外からよく見える、開かれた状態であることが必要です。そのため両者についての基本的事項が情報公開されているとともに、一定の要件を満たせば誰もが参入できることが必要です。
- 目的共有の原則
- 独自の目的や使命を持ち自律的に活動を行う市民公益活動団体と行政との間で協働関係が成立するには、意見交流と積極的な情報提供を行うことによる相互理解への努力を通して、目的の共有を図ることが必要です。
(4)協働関係の構築の留意点
市民公益活動団体は、組織的な活動や事業実施、資金調達などについて揺籃期にある段階から、行政などとも対等な関係を形成し、その社会的責任を果たしつつ活動領域をさらに広げようとするなど発展した段階にある団体まで様々であり、協働の内容についても協力して事業を実施する形態から専門性を活かし連携を図ることが可能な形態まであり、各団体の発展段階にふさわしい関係を構築する必要があります。
第3 市民公益活動の基本的促進策
市民公益活動の全般的な推進のために、高槻市においては、担当窓口となる市長公室コミュニティ推進室が関係課と連携を図りながら、次のような促進策の実現を目指します。
1 活動拠点としての市民公益活動サポートセンターの充実
市民公益活動団体の自立的発展のためには、各分野を越えた総合的なサポート機能を持つ活動拠点の整備が重要です。総合計画に掲げられた方針や市民活動促進懇話会報告書を受け、平成15年3月、西大冠小学校の余裕教室を活用して開設した市民公益活動の推進拠点である市民公益活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の一層の充実を目指します。
2 情報の収集・提供
市民公益活動団体間の交流や市民の活動参加促進のための団体情報、催し物情報などの収集・発信をはじめ、協働促進に関わる行政情報などについても提供できる体制づくりを目指します。
3 相談体制の充実
市民公益活動に参加を希望する人の相談に応じることや団体の立ち上げ、団体運営のための相談など、サポートセンターの役割の一つとして相談体制の充実が図られるよう目指します。
4 広報・啓発の充実
市民公益活動についての一層の理解と社会的認知を高めるとともに、活動への参加促進を図るため、ITの活用やフォーラムなどの催しの開催等を通じて広報・啓発の充実を目指します。
5 人材の育成
きっかけづくりの学習機会の提供等による市民公益活動への参加を広げる分野や、マネジメント研修を含め活動を支えるスタッフ育成の分野など、市民公益活動団体が行う事業とも連携しながら、人材育成に向けた取り組みの充実を目指します。
6 公共施設活用のためのサポート
市民公益活動団体が行う研修会や会議、各種の催しを開催する場合は、公民館や文化施設などの公共施設を利用することが多くなりますが、自主的な資金確保で自立した活動を行うための収益を伴う事業の開催には、物品販売の禁止規定や使用料の加算措置など市民公益活動の実態との関係では課題もあります。公共施設利用の公平性確保や法令等による位置付けを基本とし、事業の共催や後援などの手法によるサポートを目指します。
7 資金面での情報提供
市民公益活動推進のための資金確保については、協働に係る事業委託や補助金制度、基金や助成団体の制度を活用した資金交流などがあります。
行政からの資金のみに依存する体質を助長することなく、自主的で自立的活動を推進する視点から、事業委託や事業補助などによる資金交流について、今後のあり方を含め研究を進めることを目指します。
また、市民公益活動を支える助成団体(資金等提供団体)の情報について、その収集・提供に努めます。
第4 市民公益活動サポートセンターの役割と充実の方向性
1 サポートセンターの役割
サポートセンターは、市民公益活動の活性化・自立化のための環境整備として、施設・機能の提供とともに、市民が様々な活動に参加・参画するきっかけづくりの場の提供、市民・市民公益活動団体・事業者・市相互のネットワークづくり、協働の促進のための事業など、幅広い役割を担っています。市民へのPRと活用の促進を図りながら、各種情報の受発信、団体間の交流促進、学習機会の提供などの事業分野から取組み、順次、市民公益活動に関する専門的な相談、人材育成などの機能の充実を目指します。
(1)主な事業分野
1)当面推進する事業分野
イ サポートセンターの施設・設備等の提供に関すること
ロ 市民公益活動に係る各種情報の収集、提供、発信に関すること
ハ 市民公益活動団体間の交流の支援に関すること
ニ 市民公益活動に係る学習機会の提供に関すること
ホ 市民公益活動に係る相談に関すること など
2)順次実現を目指す事業分野
イ 市民・市民公益活動団体・事業者・市の各種連携の促進に関すること
ロ 市民公益活動団体の運営支援(マネジメントサポート)に関すること
ハ 市民公益活動に係る人材育成に関すること など
(2)主な事業内容
イ サポートセンターの各種設備の整備による活動条件の充実
ロ サポートセンターの団体登録の推進による活用促進
ハ インターネットを利用した情報受発信・交流機能の充実
(サポートセンターホームページの開設、関係団体間メーリングリストの確立、電子掲示板等)
ニ 市民公益活動情報紙、ハンドブック等の発行による情報提供・啓発促進
ホ 市民公益活動啓発講座等の企画・開催
ヘ 「高槻まちづくり塾」等参加しやすい体験プログラムの企画・開催
ト 組織運営やネットワーク促進等に関する相談の充実
2 サポートセンターの運営
様々な分野で活動する団体のニーズを捉え、活動基盤の強化の役割を担うサポートセンターには、市民公益活動団体で活動を行う市民自らが、その経験や活動の特性を発揮して運営に関わることが重要です。
平成13年度に公募市民が参加して取り組んだ高槻市市民活動促進懇話会以後、引き続き活動の促進を担う主体として、各種団体やボランティア・NPOなどの市民が参加する連合組織「たかつき市民活動ネットワーク」が設立され、平成15年3月、同組織との連携によりサポートセンターの管理運営委員会が組織されました。管理運営委員会と市は、サポートセンターの運営に関する覚書を交わすことにより、市民の参画・協働で行う運営形態を実現し、市民ニーズに応える施設づくりを目指しています。
また、運営の公平性や透明性の確保、充実した事業の展開を図る視点から、市民等の参加を得て第三者機関を設置し、継続的な評価手法の確立を図ります。
<高槻市市民公益活動サポートセンター運営体制>
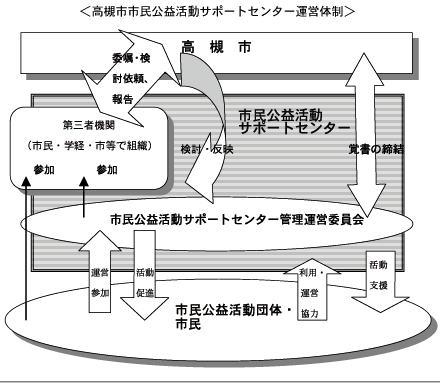
3 既存の関係機関等との関係
サポートセンターには、高槻市社会福祉協議会が設置する高槻市ボランティア・市民活動センターを始め市民公益活動各分野のセンター的機能を有する機関、企業のボランティア推進窓口等との連携の確立が求められています。 特に、高槻市ボランティア・市民活動センターについては、地域福祉活動の推進、ボランティア活動の啓発・支援の取組みなど、福祉分野での特性を活かした領域を中心に担当しており、サポートセンターの目指す幅広い分野の市民公益活動団体の活動促進、多様な市民公益活動団体間の交流推進などの取組みと相互に役割分担をしつつ、総合的に市民公益活動の促進が図られるよう連携策を講じることを目指します。
資料
資料1:ボランティアについて
ボランティア活動の意味(volunteer activity)
ボランティア活動とは、一般的には、「自由意思に基づき、主体的に他者が生活をしていくうえでの困難や社会が存続していくうえでの困難、また、よりよい社会づくりへの必要性に心が動かされ共感し、それらの解決や改善、実現のために個人がもっている内発的な力を発揮する活動」をさしている。基本的な性格としては「自発性(自主性)」「無給性(無償性)」「公益(公共性)」「創造性(先駆性)」等がいわれている。
ボランティア(volunteer)
社会をよりよくしていくため、自分の技能と時間を自主的に無報酬で提供する人たちをいい、その活動に対する関心は阪神・淡路大震災以降、特に高まっており、高齢社会の到来で、在宅福祉サービスの需要が増え、地域住民によるボランティア活動も重要になっている。最近では、サラリーマン、高齢者自身の参加も増えており、その活動を通して生きがいを見出している。都道府県・市町村の社会福祉協議会に、ボランティアセンターが設置され、情報を提供している。学校教育、社会教育を通してボランティア活動が取り入れられ、層も広がり、活動内容も多岐にわたり、地域に根ざしたものが多くなった。
(自由国民社刊「現代用語の基礎知識」1999、2002より)
資料2:NPOについて
NPO(Nonprofit Organization)は、民間の非営利組織のことで、福祉や環境、人権問題などの社会的な課題に、市民が主体的に取組んでいる組織を指します。
日本を含む世界12カ国の民間非営利セクターを分析する試みを行った「ジョンズ・ホプキンス大学非営利セクター国際比較研究プロジェクト」は、「非営利セクター」の特徴として(1)正式に組織されていること、(2)民間であること、(3)利益配分をしないこと、(4)自己統治していること、(5)自発的であること、を挙げています(L.M.サラモン他著『台頭する非営利セクター』より)。
これらの特徴をもつ団体には、法人格を持たないボランティア団体から特定非営利活動促進法に基づいて認証された特定非営利活動法人(図1:「最狭義のNPO」)、財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、政党、宗教団体、労働組合、自治会などの地縁団体、同窓会など非営利の民間団体の全てが含まれることになります(図1:「最広義のNPO」)。
平成12年度版国民生活白書では「NPOにどのような団体が含まれるかは、いろいろな考え方が存在していて使われ方は統一されていない」のが現状としつつ、「NPO法人や法人格を取得しない市民活動団体・ボランティア団体」をNPOとして取り扱うとしています。本推進方針では、同国民生活白書を参考に、特定非営利活動法人や法人格を取得しない非営利の社会貢献団体をNPOとして取り扱っています(図1:「狭義のNPO」)。
多様なNPOと定義上の関係(図1) (高槻市市民活動促進懇話会報告書資料を参考に)
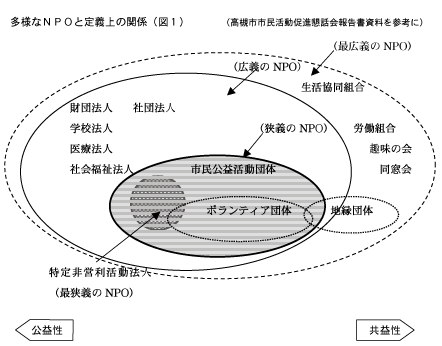
資料3:特定非営利活動促進法(NPO法)について
民間の非営利団体(NPO)は、福祉、まちづくり、環境、国際交流、青少年の健全育成などの様々な分野で、市民社会を取り巻く課題解決のための社会貢献活動を展開し、その存在と重要性が広く認められるようになっています
しかしながら、NPOの多くは任意の団体として活動しているため、団体名で、銀行口座の開設や電話の設置、不動産登記などの法律行為を行うことができず、その対応が求められてきました。そこで、平成10年3月、こうした団体に簡便な手続きで法人格を付与することにより、自由で健全な活動を促進し、公益の増進を図ることを目的として、特定非営利活動促進法(通称NPO法)が制定されました。
特定非営利活動法人になるには
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
- 特定非営利活動(注1)を行うことを主たる目的とすること。
- 営利を目的としないこと(注2)。
- 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
- 10人以上の社員(正会員など総会で議決権を有する者)がいること。
(注釈1)特定非営利活動
(1) 次に該当する活動であること(法第2条の別表に掲げる活動)
一 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女協働参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
一六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること。
(注釈2)営利を目的としないこと
構成員(社員、役員)に利益を配分しないことや財産を還元しないこと、解散の場合にも、残余財産を構成員に返還しないことをいいます。
(資料3は、大阪府発行「特定非営利活動促進法(NPO法)のあらまし」を、法律改正により一部修正して引用しています。)

