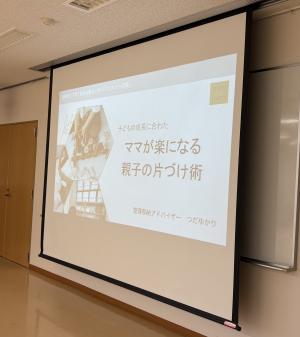本文
親子講座「ママが楽になる 親子の片付け術」を開催しました
令和7年10月23日(木曜日)に整理収納アドバイザーIPPO IPPO津田由加里さんによる親子講座「ママが楽になる 親子の片付け術」を開催しました。
まず、参加者同士で自己紹介をし、片付けに関しての「もやもや」「わくわく」することを話し、困りごとなどを出し合ってもらいました。
次にママが楽になる片付け術の5つのコツを教えていただきました。(1)「一緒に使うモノをまとめる」では、おむつセット(おむつ、おしりふき、マットなど)やお出かけセットなど、用事ごとで使うモノをまとめておくとよいとのことでした。(2)「『とりあえずボックス』を作る」では、一時的な置き場所を作ることにより、心に余裕を持てるようになるそうです。家族の一人ひとりのボックスを作り、ボックスがいっぱいになったら中身を見直すといいとのことでした。(3)「片付けのタイミングを決める」では、夜寝る前だったり、朝起きた時だったり、毎日5分は片付けをするなど、自分自身の生活リズムに合うタイミングを見つけ、習慣化していくことが良いそうです。(4)「ゴールデンゾーンを意識する」では、モノを使う際には、使いやすい高さがあり、それが目線の位置から腰の高さくらいだということで、よく使うモノをその位置に収納することにより、片付けもしやすくなるということでした。(5)「完璧を目指さない」では、子どものいる暮らしでは常にきれいな状態を保つことはできないので無理をしないと決めて少しずつ片付けるといいとのことでした。
また、整理収納の基本ステップを守ることが元に戻らないコツだということです。整理>収納>お片付け>整頓掃除のステップで進めます。整理収納作業の8割が整理となります。整理というと「モノを捨てないと!」と考えてしまいがちですが、捨てるものを探す作業と考えるとしんどくなる方もいると思います。まずは「いる・いらない」「使っている・使っていない」「好き・嫌い」に分けるところから始めるとよいとのお話でした。
そして、子どもの成長に合わせた関わり方のヒントとして、子どもの誕生から1歳では衛生面と安全面を最優先します。いつもの場所、いつもの手順が子どもの安心につながります。モノの定位置を決め、いつもの流れでお世話ができるような環境を整えます。2歳から3歳(イヤイヤ期)は子どもの「やりたい」という気持ちを優先し、順序立てて伝えることが大事です。「片付けて!」と伝えるのではなく、「このおもちゃをこのカゴに入れて、ここの棚に戻してね」など具体的に伝えるとよいとのことです。この頃の子どものゴールデンゾーンは低い位置なので、子どもに手を触れてほしくないモノは上の位置に置くことで余計な注意をしなくて済むようになります。4歳から6歳(集団生活を体験する時期)は子どもの好奇心とやる気をサポートするような働きかけをするとよいそうです。一緒に決める、選ばせる、適量を守らせ、要不要の判断は子どもの意思を尊重しましょう。
最後に片付けは「情操教育」につながります。情操教育とは他者を思いやる気持ち、豊かな感受性、想像力、美的感覚、道徳心を育む教育ですが、片付けをすると気持ちが良かったり、どのように片付けるとよいか想像したりもできます。整理整頓を日々心掛けることで、本当に必要なモノを選び取る力がつくようになります。人生は色々なことを自分で決断、判断していくことの連続です。整理整頓をすることはその練習にもなります。
子育てで忙しい日々ではありますが、整理整頓を心掛け、生活環境を整えることが子どもの成長にもつながることを教えていただきました。
子育て総合支援センターではさまざまな講座を開催しています。市ホームページやたかつきDays(広報誌)をチェックしてみてくださいね。